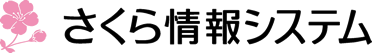技術開発部 統括部長
COLUMN
コラム
BizTechコラム
ハッカソン
さくらハッカソン2020開催(インターン学生向け)準備編 ―コロナ禍でも開催した理由とその方法―

森 隆彦
2020.10.23
2020年夏、昨年に続き今年もインターン学生向けに「さくらハッカソン」を開催しました。今回のコラムでは準備編、次回コラムでは当日編と2回に分けて掲載します。
新型コロナ感染症の影響で春の「さくらハッカソン」開催は中止に
2020年4月7日、新型コロナ感染拡大防止を目的とした緊急事態宣言が発令され、オフィス勤務は在宅勤務へ、対面での打ち合わせはWEB会議へなど、仕事のスタイルは大きく変化しました。実は当社では3月に春のハッカソンを企画し、学生のエントリー受付を開始している状況でしたが、これも中止を余儀なくされました。
その中で、5月に入り、「大学生前期すべてがオンライン授業に」といったニュースが目に飛び込んできました。また、当社での2021年新卒採用もすべてオンラインに切り替わっており、採用担当者から「学生は日々オンラインで授業を受けているので、これまでとの状況の違いに戸惑いながらも順応している」という声を聴いていました。ここで、ふと「コロナ禍を理由に学生向けのハッカソンをあきらめてよいのか?」「学生が企業を知る機会であるインターンイベントを何らかの形で提供できないか?」そのような思いが私の中を巡りました。
オンライン開催での苦労とその準備
そこで、インターンを取りまとめている人事部と協議の上、8月下旬の5日間に完全オンライン形式でのインターンハッカソンを開催することを決めました。
ただここからが苦労の始まりで、以下のような数多くの課題を解決しなければなりませんでした。
1.テーマ選定と目的設定をどうするか?
2.非対面の制約をどのように解決するか?
3.コミュニケーションを活発にするためにどうするか?
4.開発環境(プロトタイプ構築)をどうするか?
5.学生の「困った」をすぐに解決する体制はどうするか?
1.テーマ選定と目的設定をどうするか?
まずはすべての原点であるテーマ設定と学生インターンハッカソンの目的です。
目的については、「学生に実際のIT開発の経験から当社を知ってもらい、さらにはIT業界で働くことの楽しさを体験してもらう」とし、昨年設定した目的を変更せずに継続することにしました。
一方、テーマについては、学生自身がコロナ禍の環境変化の中で、オンラインを中心とした学生生活に苦労を感じていることから、「コロナ禍における課題をITを用いて解決する」ことにしました。
5日間のタイムスケジュールは以下の通りです。


2.非対面の制約をどのように解決するか?(チームビルディング)
何より解決すべき課題は、対面での開催からオンライン開催にすることでした。私の所属部署でもすでにZoom*1を活用して在宅勤務中の社員とコミュニケーションをとっていましたが、その前提はメンバー全員がすでにチームビルディング出来ている状態であったことでした。
各大学から参加するメンバーは、「はじめまして」からのスタートのため、以下3つの取り組みからチームビルディングをしっかり行うための活動に時間を多くとることにしました。
・開催1週間前に事前ガイダンスをZoomで行い、このタイミングで自己紹介など顔合わせを実施
・開催初日の午前中に、2チームに分かれて改めてハッカソンに参加した目的や期待などをディスカッション
・活動期間中、開始時と終了時にチェックイン、チェックアウトを行い、メンバー同士で今の気持ちをシェア
オンライン開催を成功させるための重要なポイントは、限られた活動の中でいかに効果的にチームビルディングを行うかだと考えました。
3.コミュニケーションを活発にするためにどうするか?(Zoom、Slack、Miro)
以下のツールを上手く使い分けて、メンバー間のコミュニケーションを取ることにしました。
・WEB会議ではZoomを利用
・テキストでのコミュニケーションはSlack*2を利用
・設計時などに用いるツールはMiro*3を利用
Zoomは、5日間接続し続ける状態にして、いつでも会話可能な状態を作るのはもちろんのこと、ブレイクアウトルーム*4を活用してチーム別の活動を円滑に行えるようにし、チーム活動と全体活動にメリハリをつけて運用することにしました。
Slackは、テキストベースでのコミュニケーションはもちろん、資料の共有や他チームへの状況の共有などに活用しました。
Miroは、今回の活動で利用するビジネスツールや振返りの為のツールなどをチーム内で円滑に議論するため、活用することにしました。対面だとホワイトボードや付箋を用いてメンバーでワイワイガヤガヤを繰り返しながら進めていきますが、今回はこれをWEBベースで行うようにしました。
4.開発環境(プロトタイプ構築)をどうするか?(Obniz、AWS Lambda)
今回も前回と同様、学生にIoTベースでプロダクトを模索してもらおうという前提に立ち、IoTでかつオンラインで手軽に開発が可能な環境を準備する必要がありました。
そこで着目したのが、Obniz*5というIoTボードです。Obnizとは「IoTサービスをすぐに始められるオールインワンプラットフォーム」と開発元の公式サイトで紹介されている通り、IoTデバイスを制御するOSと開発環境を併せて提供するクラウド環境がセットになったプロダクトです。インターネットを使うことが出来ればすぐにでもIoTセンサー制御と実現したい機能が構築できる、今回の活動に必要な手段として非常に有効なものと判断し採用しました。
また、センサーで取得したデータを保存するシーンも想定して、AWS Lambda*6を利用したAPIの構築など、ハッカソン当日に利用できるソフトウエア部品を準備しました。今更ですが、クラウドが利用できる時代で良かったと改めて感じます。
5.学生の「困った」をすぐに解決する体制はどうするか?(社員も参画)
今回はすべてオンラインでの実施です。そのため各3名の学生チームに専属の先輩社員エンジニア1名をメンバーとして参画させ、チームの進捗管理や活動中に発生した不具合などを一緒に解決する仲間として、フォローが出来る状態を作ることにしました。この体制で臨むことにより、社員と学生の距離も近くなり、より学生達に当社のこと、ひいてはIT業界で働くエンジニアのことを知ってもらえるのではないか、という思いも込めて準備を進めました。
準備編はここまでになります。次回の当日編は参加学生6名と先輩社員エンジニアによる5日間の様子をお伝えしたいと思います。
*1 Zoomは、Zoom Video Communications, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
*2 Slackは、Slack Technologies, Inc.の登録商標あるいは商標です。
*3 Miroは、RealtimeBoard, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
*4 Zoomの機能で、ミーティングに参加している参加者を小さなグループに分けることができる機能のこと。
*5 Obnizは、株式会社CambrianRoboticsの登録商標です。
*6 AWS Lambdaは、米国その他の諸国における、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
著者プロフィール

森 隆彦
お客さまのビジネスに貢献するITサービスの提供を、ITアーキテクトとして戦略的情報化企画から開発、運用まで、幅広くアシストします。エネルギー系企業や金融系企業などのシステム構築経験をバックボーンに、高可用性が求められるシステム開発における非機能要件定義やデータモデリング、パフォーマンスチューニングを得意としています。また、社内外のITアーキテクトコミュニティの運営にも携わり、ITアーキテクト職の啓発および後進の育成を推進しています。
※ 所属部署・役職は2021年3月以前のものです